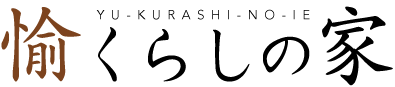株式会社 大功 × 国立学校法人 千葉大学
サンブスギを活用した地産地消の家づくり
サンブスギを活用した地産地消の住宅作りを、千葉大学との産学連携プロジェクトとして開発し、地域資材の価値を広く社会に伝えることも目的としています。 県産材の特徴や住宅の木質化による健康面への効果などの研究により裏付けられた住みよい住宅をご提案し、地域活性化へと貢献します。
背景と目的
千葉県内の里山再生と経済循環のために、サンブスギをはじめとした地域産材の活用を推進しなければなりません
- 日本は人工減少時代を迎え、林業や建設業など、住宅建設に関わる地域密着型の産業は大きな転換期を迎えています。
- 国内の森林資源は安価な外国産材に太刀打ちできず、担い手不足や高齢化と相まって、衰退が続いています。
- 千葉県内にはサンブスギという地域産剤がありますが、上記の問題や疫病被害などによって十分な活用がなされていません。里山保全の面でも、こうした県産材の活用・流通のための新しい方策が求められています。
- 地域の事業所が元気になることは、地域家政科の視点においても重要です。県内材の活用を促すことができれば、森林資源の循環と地域経済の循環の両面から地域活性化に貢献することができます。
- よって本研究は、サンブスギを活用した地産地消の住宅を産学連携で開発し、地域産剤の価値を広く社会に伝えることを目的としています。

研究計画
学生とともに先行事例調査やヒアリング調査を実施し、地域産剤の特徴や課題、木材の効果の把握をおこない、地産地消の家造りのコンセプトづくりに取り組みました。
フェーズ1:サンブスギの特徴と課題の整理
- 日本や千葉県の林業の抱える問題の把握(ウェブ、広報物、出版物等)
- 本研究に関連する先行事例調査(論文、出版物等)
- 県内関連機関へのヒアリング(木材組合、山武市、研究者、民間事業者等)
フェーズ2:木材の効果の把握とモデル住宅の木質化の検討
- 木材利用の効果に関する選好研究調査(林野庁、森林研究センター等)
- 研究者へのヒアリング(千葉大学園芸学部)
- 内装木質化の検討(CGIによる検証)
フェーズ3:地産地消の家造りのコンセプトとブランドメッセージの立案
- ブランディングの定義(文献等)
- ターゲット層の嗜好の把握(出版物等)
- コンセプトとブランディングの検討
研究成果① サンブスギの特徴と課題の整理
強度があり、赤みの強いサンブスギは建築材に適している一方、
非赤枯性溝腐病が蔓延し、安定的な供給が難しいという課題を抱えています
サンブスギの特徴
- 一般的なスギよりも硬く、長持ちする住宅を作るのに適しています。クローンの挿し木にのため、育つ速度が同じで、まっすぐ育ち、均質な大きさとなります。
- 一般的なスギよりも油気が多く、艶や木肌の色が良く、赤みが強い特徴があります。
- 花粉を飛ばす雄花をほとんど付けないため、花粉の少ない優良品種の一つとなっています。
サンブスギの課題
- 木材の腐朽菌による病害である杉非赤枯性溝腐病が蔓延しています。腐朽したサンブスギの財貨は著しく低下し、再利用の方策も少ないです。
- 地域産剤としてのブランドが弱いです。たとえば、カタカナの「サンブスギ」は山武地方において古くから育てられてきた挿し木を指す一方、漢字の「山武杉」は主に山武地方に生息する杉全体を指しており混乱を招いています。
- 材料の安定的な確保が難しい材料です。溝腐病による被害や需要の少なさから、流通する良質なサンブスギは限定的となり、需要に合わせた柔軟な仕入れが困難となっています。
このようなことから、サンブスギは住宅剤に適しているものの、社会的な課題から活用方法が見いだせずにいます。その結果、里山の後輩や林業の衰退に繋がり、流通する材料が減り、活用機会が失われるという悪循環に陥っているとも考えられます。
研究成果② 木材の効果の把握とモデル住宅の木質化の検討
木材を使う事による環境的・生理的な効果は
これまで多くの研究がなされており、一般的に認められてます
- 木材を利用する住宅は健康によいと考えられています。木材を使った住宅はストレスが少なく、リラックス効果を高めることが分かっています。より良い睡眠や生産性が向上し、日々の生活を豊かにすると考えられています。
- 木材の利用は、住宅の性能を向上させることができます。防湿性や断熱性の向上により、より快適に過ごせます。
- 木材を利用することは、地球環境に貢献することでもあります。木材は再利用ができ、再生産が可能な地球にやさしい材料です。木材を積極的に利用することで、温暖化防止に貢献し、持続可能な森林資源を守ることができます。